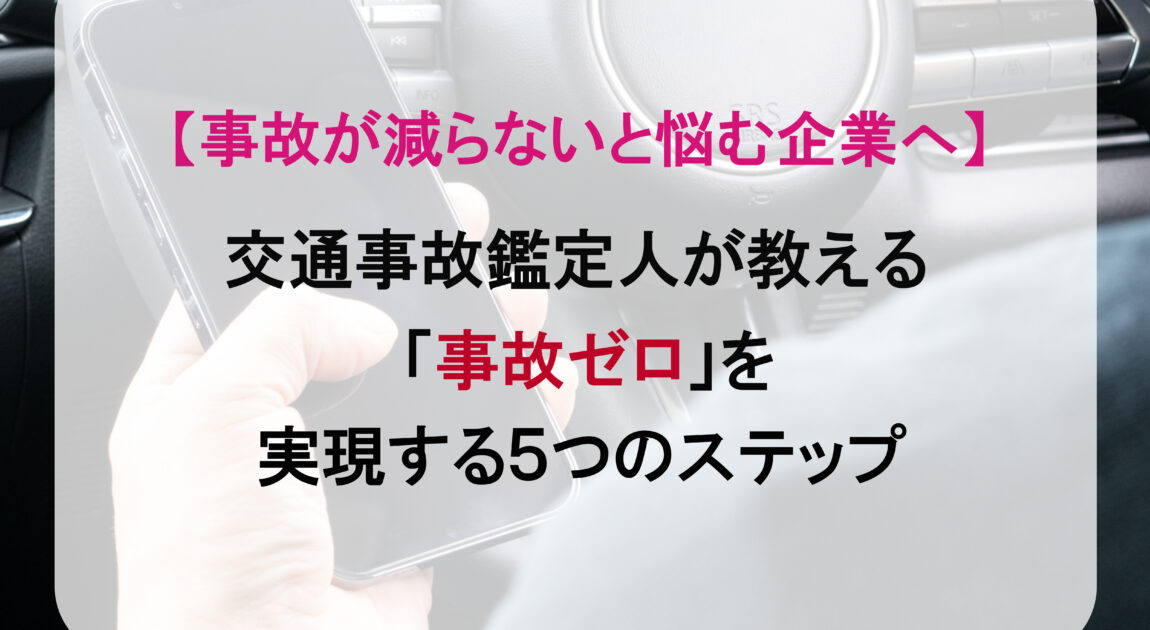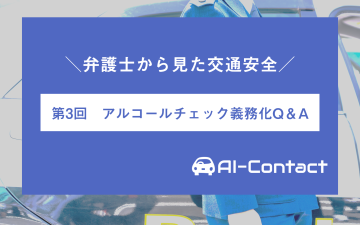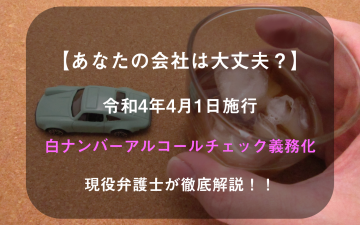2025年5月に改正された厚生労働省の「交通労働災害防止のためのガイドライン」では、企業に従業員の交通事故防止対策が強く求められています。しかし、多くの企業は「安全運転管理者」を配置していても、専門的な知見を持つ「事故削減のプロ」がいるわけではありません。
実際、研修を実施しても事故が減らない、運転日報をつけても効果が見られない、といった悩みを抱えている企業は少なくありません。
では、本当に効果のある安全運転教育とは何なのでしょうか?
この記事では、数百件の交通事故映像を分析し、事故の原因を熟知している交通事故鑑定人が、「事故ゼロ」を実現するための5つのステップについて詳しく解説します。
目次
1.交通事故の本当の原因とは?
従業員の交通事故を減らすには、まず「交通ルール」を徹底することから始めましょう。
「ヒヤリハットを減らしましょう」「Gセンサーが反応しないように運転しましょう」といった安全運転教育は、多くの企業で行われています。しかし、これらを伝えるだけでは、従業員は「具体的にどうすればいいの?」と迷ってしまうかもしれません。
大切なのは、なぜヒヤリハットが起きるのか、なぜGセンサーが反応するのかという根本的な原因を理解することです。その原因の多くは、「交通ルールの不徹底」にあると言っても過言ではありません。
たとえば、交差点での歩行者の飛び出しで「ヒヤリ」とした経験はありませんか?
これは、一時停止や安全確認を怠った結果かもしれません。交通ルールを守って、しっかり止まって左右を確認する。この基本動作を徹底すれば、急ブレーキを踏むこともなくなり、Gセンサーが反応することも減らせます。
事故処理の基準は「道路交通法」です。
万が一事故が起きた場合、その後の警察への届け出や罰金、過失割合などは、すべて「道路交通法」に基づいて判断されます。
交通事故の鑑定作業も交通違反の有無や程度を数値化する作業です。
安全運転教育の多くは、運転技術の向上やヒューマンエラーの防止に焦点を当てがちです。しかし、どれだけ技術が高くても、交通ルールを守らなければ、事故のリスクは減らせません。
「安全に運転してください」と抽象的に伝えるのではなく、「この行為は道路交通法〇条に違反し、事故が起きた場合には、このような罰則につながることがあります」と具体的に説明することで、従業員の意識は大きく変わるはずです。
安全運転教育の成功は、高度な技術や精神論ではなく、運転免許を持つ人なら誰でも知っている「交通ルールを徹底して守ること」から始まります。
従業員の安全を守るため、まずは「なぜルールを守る必要があるのか」という根本的な部分に焦点を当ててみましょう。
2.運転のシミュレーションと実践練習で、気づきを促す
道路交通法を基準に教育することで、従来の講習もより効果的になります。座学だけでなく、実際に運転をシミュレーションしたり、自分の運転を振り返る機会を設けましょう。
危険予知トレーニングを活かす
安全運転教材として広く普及している「危険予知トレーニング(KYT)」は、もし自分がその場面で運転していたらどうするかをクイズ形式で考えるものです。このトレーニングをより効果的にするには、ただ危険を予測するだけでなく、「なぜその危険が起こるのか」を交通ルールの観点から考えることが重要です。
たとえば、「見通しの悪い交差点」の映像を見たときに、単に「自転車が飛び出すかもしれない」と予測するだけでなく、「一時停止標識があるから、必ず停止して安全確認する必要がある」という具体的な行動につなげられます。もし危険予測が苦手な従業員がいれば、道路標識の意味や正しい停止位置を復習させるなど、個別に対応することで理解を深められます。
同乗による実車講習で「無自覚な違反」を発見
最も効果的な方法の一つが、担当者が従業員の運転に同乗し、日頃の運転のクセや無自覚な交通ルール違反に気づかせることです。
「一時停止したつもり」で、実際には完全に停止していなかったり、安全確認の時間が極端に短かったりなど、本人が気づきにくい違反を発見できます。従業員が多く、一人ひとりに同乗することが難しい場合は、交通違反を可視化する車両管理システムなどの導入も効果的です。

交通違反を可視化する
車両管理システムは「AI-Contact」
3.心理的な側面から事故リスクにアプローチする
どんなに交通ルールを理解していても、人の心理が運転に大きな影響を与えます。どのような心理状態や性格が事故につながりやすいのか、従業員自身に気づいてもらうためのアプローチも重要です。
心理的な要因を理解する
運転中のヒューマンエラーには、以下のような心理的な要因が潜んでいます。
① 認知バイアス
「いつも通っている道だから大丈夫だろう」という正常性バイアスや、「自分は運転がうまいから大丈夫だろう」という過信バイアスは、危険を見逃す原因になります。「だろう運転」が思わぬ事故を招くことを周知しましょう。
② 運転に適さない性格
心理学の研究では、怒りっぽい人、自分本位な人、見込みが甘い人などが事故を起こしやすい傾向にあると言われています。業務での運転が避けられない場合は、慎重な運転を心がけるよう指導するなど、個別の対策が必要です。
③ 運転前の感情に着目する
気分が高揚していたり、逆に落ち込んでいたり、平常心からかけ離れた状態での運転は事故リスクを高めます。特に気分が落ち込んでいる時は、安全確認がおろそかになりがちです。可能であれば、運転前に従業員に声をかけ、様子を確認することでリスクを軽減できます。
グループディスカッションで「自分ごと化」する
従業員同士でグループディスカッションを行うことも有効なアプローチです。教材を見ながら「この場面でどうすれば事故を防げるか」を話し合ったり、実際に自身が経験したヒヤリハットや事故の体験談を共有してもらいましょう。
身近な人の話は「自分にも起こりうること」として捉えやすくなります。
また、「こんな運転を心がけたら事故が減った」といった成功体験を共有する場を設けることで、他の従業員のモチベーション向上にもつながります。

4.継続的なフィードバックとフォローアップで習慣化する
安全運転は、一度学んで終わりではありません。継続的な教育とフィードバックによって、安全な運転習慣を定着させることが最も重要です。
運転日報や車両管理システムを活用する
日々の運転日報や車両管理システムを活用し、「見える化」されたデータを基にフィードバックを行いましょう。
たとえば、システムに記録された交通違反の回数を見て、「先週は速度違反が多かったから、今日は速度に気をつけながら運転しましょう!」といった簡単な目標を毎日設定するだけでも、安全運転への意識が芽生えます。
定期的な安全運転講習を習慣にする
安全運転講習を年に数回の「特別イベント」にするのではなく、週に1回10分程度のオンライン講習など、無理のない範囲で継続的に実施しましょう。
システムで集計された違反データから、「先週は一時停止違反が多かったため、交差点での出合い頭事故が発生しています。交差点に進入する際は、3秒以上停止して安全確認しましょう」といった具体的なテーマを設定すると、より効果的です。また、無違反だった従業員を褒める場として活用すれば、モチベーションの向上にもつながります。
5.【最も効果的な最終手段】人事評価に加える
安全運転を習慣化させる上で、最も強力なのが「人事評価」への組み込みです。
交通違反の少なさを「低リスクドライバー」として評価し、安全運転手当を支給するなど、金銭的なインセンティブを設けることで、短期間で大きな効果が期待できます。
実際に、安全運転の評価を人事制度に取り入れた多くの企業が、年間の事故数削減と自動車保険料の削減を実現しています。
「安全運転をしてください」と伝えるだけでは、もう十分ではありません。
なぜなら、ドライバーは「何をすればいいか」を具体的に知らないからです。
大切なのは、事故の本当の原因を理解し、従業員一人ひとりが「自分ごと」として安全運転を捉えられるように導くことです。
貴社の従業員は、安全運転の本当の意味を理解していますか?
この機会に、従業員の命と会社の未来を守るための、一歩踏み込んだ安全運転教育を始めてみませんか?

交通違反を可視化する
車両管理システムは「AI-Contact」